ペンネーム ウルトラマン

目次
私は彼に、腕立て伏せ40回を命じたところだ。
リンク
読者諸兄も御存知なように、
リンク
「救急隊が帽子を脱ぐ時はいつだ!!」腕立てを終えた彼は、
———
そして今、私は二つ目の帽子を脱ぐ場面に遭遇しようとしている。
妻が出勤する時、台所で新聞を読んでいた夫は、いつものように「
死亡宣告の瞬間、すでに私たちの頭に帽子はない。
けるという行動をとる。その少しだけ近づけた頭で、
リンク


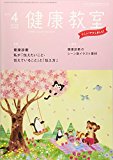
コメント