月刊消防2019年2月号p89
ペンネーム:月に行きたい
「敵」という発想はいらない
係長が電話越しに誰かと喧嘩をしている。
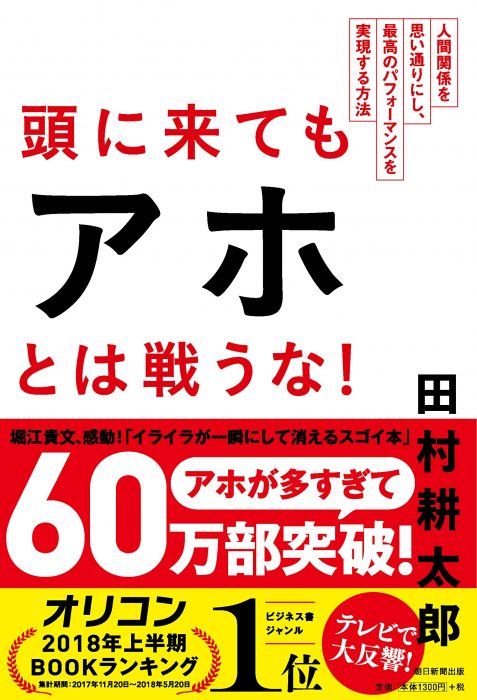
「対人関係を捉える時に知っておいてほしいのは、まず「敵」
リンク
リンク
私にも苦手な人はいる。その人と私の関係は、
田村さんは、「相手と戦って、たとえ表面的にでも論破し、
とはいうものの、
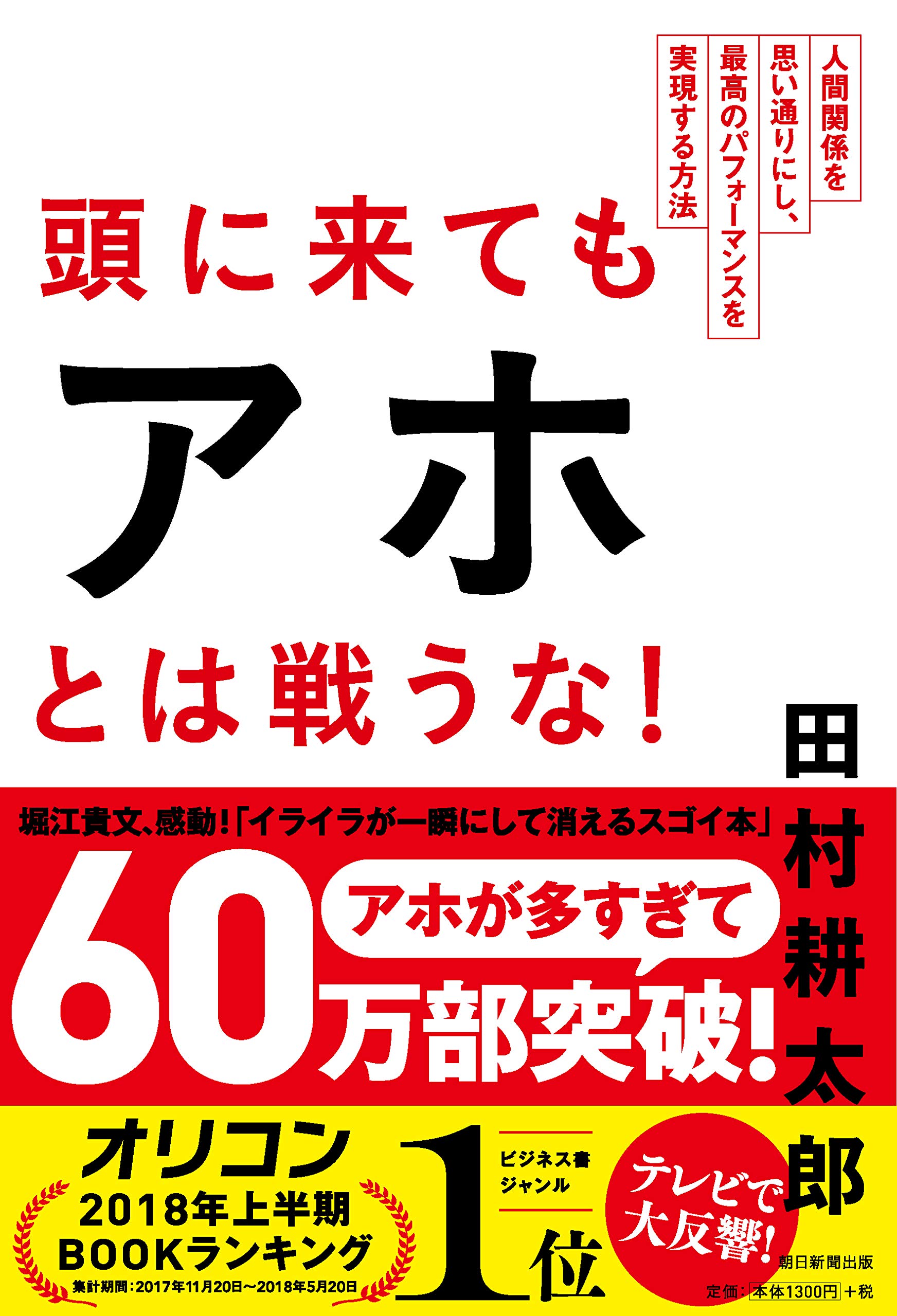

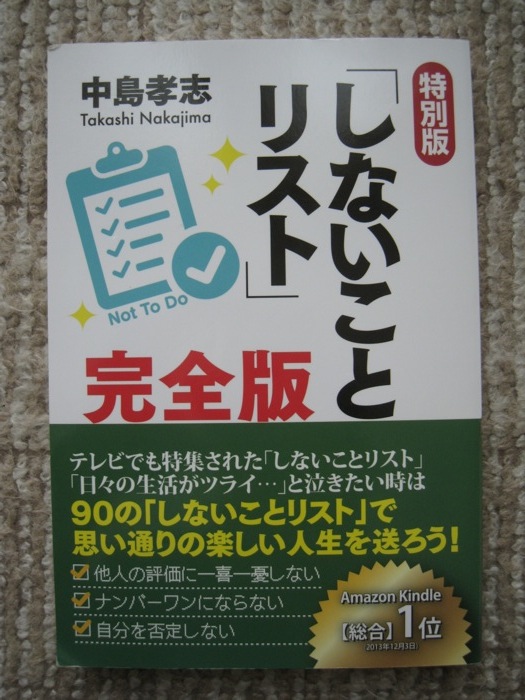
コメント