近代消防 2024/05/11 (2024/06月号)p86-8
みなさんこんにちは。前回に引き続き、発表スライドの作り方を解説します。
探せば題材が見つかる症例報告と違い、研究報告は計画して行動しなければ発表に至りません。なのでスライドも質が高いものがほとんどです。しかし特にデータの示し方で残念な発表を見かけることが多いような印象です。
目次
1.原則
(1)結論=ゴールを常に頭に置く
研究報告は症例報告より結論がはっきりしているはずなのですが、スライドを見ても発表原稿を見ても何が言いたいのかわからないことがあります。結論を常に意識して発表を組み立てます。

001
この抄録にはちゃんと結論が書いてあります。この結論に沿って矛盾なく発表を組み立てます。
(2)グラフを使う。表は使わない。
生データを表で示していることがあります。必ずグラフにします。ですがグラフの選択を誤ると間違った印象を与えますのでグラフは慎重に選択します。

002
こういう数字だけ出されて理解できる人はいるのでしょうか。

003
002と同じ演題ででてくるグラフ。患者番号を横軸に持ってきているのが間違いです。

004
002の演者は、自分でも分かりづらいと思ったらしく表を出してきました。要するに、差がある項目とない項目があるらしい。私なら前後の変化を%で示して分散分析を行います。
2.各パートで気をつける点
(1)題名:可能なら結論を書く

005
題名は「~をやってみた」という研究の内容を書くのが一般的ですが、結論を書くこともあります。

006
結論を題名としてみました。インパクトはこちらの方が上です。ただ好みがあります。私は一本道で結論まで行ける研究に関しては結論を題名にするようにしています。
(2)対象と方法:写真を載せる

007
通常は文字だけで説明します。

008
ここに写真をつければ、何をどうやったかすぐ理解できます。
(3)結果:グラフ!グラフ!!

009
とにかくグラフです。元データを示しますが、これでは理解できません。「そんな、表で出してくるヤツなんているのか」と思うでしょうけど、たくさんいます。

010
009をグラフにしたものです。くっついているのが1セットで、3本の棒にはそんなに差がないことがすぐ分かります。
3.良い発表をするには
(1)他人の発表を見る

011
色々な発表を見ましょう。学会発表だけでなく、勉強会や講演会など。分かりやすい人もいれば何言っているか理解できない人もいます。目の前の発表がなぜ理解できる(できない)のか考えれば、自分の発表に反映することができます。
(2)指導してもらう
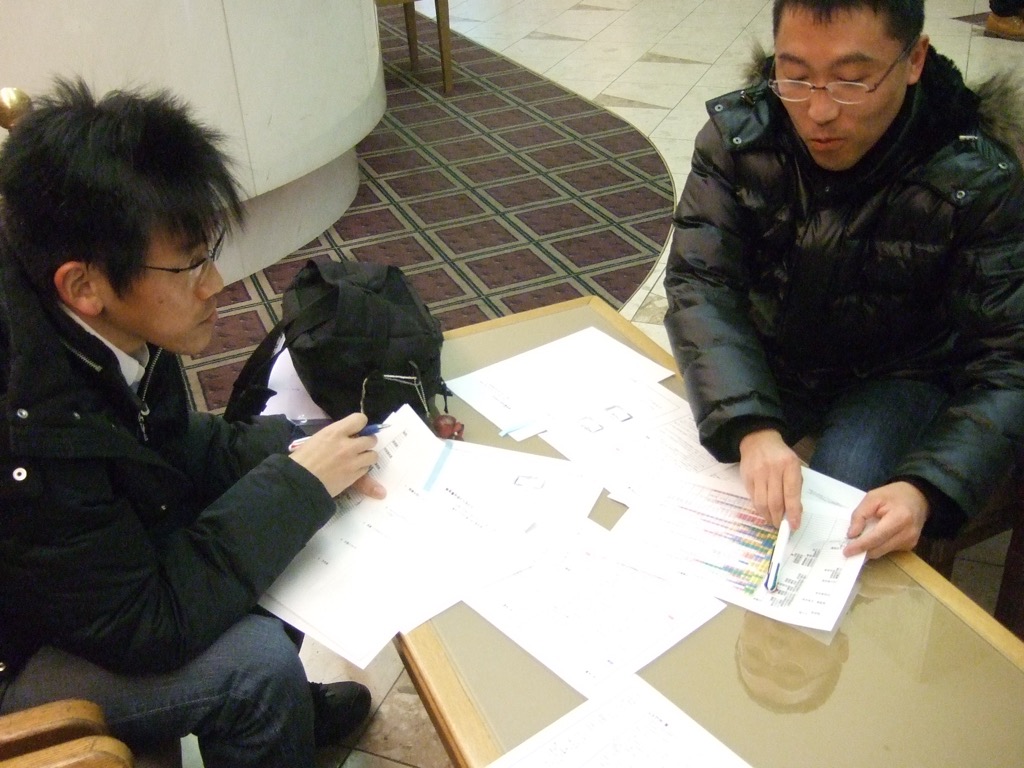
012
経験者がいればその人に指導してもらうもの有効です。ただこの場合は指導者の質が問題になります。信頼でき、さらに発表者の意図ややる気を曲げないような人なら有効な指導となるでしょう。
4.終わりに
この2回の連載では、見せ方に焦点を当てて解説しました。症例の探し方や研究の組み立て方はそれぞれ方法があります。例えば、症例は特異なものでなくても数を集めれば発表できますし、日常の活動でちょっとした疑問や不自由があれば全て研究に持っていくことができます。今回の連載が皆さんのお役に立てることを願っています。
引用
007から010:井出優。近代消防2022年11月号p82-85



コメント