プレホスピタルケア2019年4月号, p52

現在救急隊による活動はメディカルコントロールの枠内で行われており、行動の一つ一つが医師の助言や指導の対象となっている。だが志の高い救急隊員と話をすると、「現場のことは我々救急隊員が最も知っている」と言い「現場学を早々に確立しなければ」と主張する。確かに私など現場活動はしたことはないし、現在最も旬である集団災害のセミナーにしても、現場のスペシャリストである救急隊員が現場にほとんど出向いたことのない医師から現場のことを教わることに矛盾を感じる。
現場には現場特有のノウハウがあるはずだ。だが、ノウハウは学問とは言えない。「このネジはこう回せば抜ける」と同じレベルだからだ。「現場学」を確立するためには再検証可能な結果と理論の積み重ねが必要であり、積み重ねの手段として論文がある。
救急隊によるエビデンスは気管挿管だけ
リンク
2014年とちょっと古いが、イギリスから「Critical care paramedics: エビデンスはどこにある」という総説がでている1)。Critical careとは「救急救命」「瀕死の患者を助けること」を指す。Paramedicは日本では救急隊や救命士のことである。論文では「救急隊が病院前救急救命を提供するという概念は世界中に広まっている。ここでは日常的に病院前救護に当たっている救急隊が現場において何らかのエビデンスを作り発表しているか、過去に発表した論文を調べてみる」としている。回りくどい言いかたをしているが、つまり救急隊だけが携わって質の高い論文が出せるか調べてみる、ということである。
筆者らが探し当てた救急隊の論文は12編。無作為抽出のコントロール研究は1編のみで残り11編は後ろ向き研究であった。5編は救急隊と医師との共同の治療結果で、そのうち3編は医師の治療によりよい結果がもたらされたもの、2編は結果に変化はなかったものである。4編は「救急隊員」と「医師ではない人たち」のケアを比べたもので、2編は救急隊が良い結果を挙げ、1編は項目ごとに優劣が異なり、1編は両者で差がなかったとしている。3編は救急隊の技術を研究対象としていて、そのうちの1つが救急隊による現場での気管挿管を扱っており良い結果を報告している。救急隊による気管切開についても取り上げており、気管切開に伴う合併症発生はどの隊でも差はないこと、非侵襲的な気道確保は患者の長期生存に影響しないことが書かれている。
筆者らは結論として、救急隊による救命救急にかかわるエビデンスは気管挿管くらいしかないので、さらにレベルの高い研究が必要としている。
リンク
技術にもエビデンスが欠けている
これも2014年に同じ雑誌に掲載されたものである2)。救急隊員が持つ技術にエビデンスがあるかどうか、項目を分けて過去の論文に当たって調べた。その結果は以下の通りである。筆者らは、救急隊の持つ技術は多岐にわたるがそれぞれガイドラインとして定めるにはエビデンスが弱いと結論している。
1)患者評価と対応計画
9編が該当した。60歳以上の患者に対する対応はよく患者や関係者からの評価は高いものの、ルーチン以外の患者に有利な資源を提供する能力は低い。また割合の低い患者層への対応技術、例えば小児に対しての対応技術も低い。これは対応技術を獲得するには多大なモチベーションが必要なことが低い技術の理由であろう。
2)健康についての情報や知識を取得すること
カナダから1編論文が出ている3)。1時間半の講習を受けてもらい、その後の行動が変化したかを活動報告書から拾ったものである。その結果、講習の前、講習の1ヶ月後、講習の1年後で行動に変化はなかったとしている。
3)安全管理
アメリカからの報告4)では、救急隊は他人の家の内外でのリスク認識には優れているが、持続的・もしくは長期の安全管理については認識が欠けているとしている。アメリカの救急隊員は一人当たり257戸の家を担当しており、そこには49丁の銃が所持されている。さらに一酸化炭素中毒の現場に出場する場合にははじめから一酸化炭素が充満してることを情報として得られるのが68%であり、残りは事前情報なしで家に入ることになると警告している
4)教育
2つの論文が教育について論じており、いずれも高評価かを与えている。
5)論文の質
救急隊を扱った論文のうち優が4編、普通が8編、劣が2編であった。研究方法に無作為コントロール法を採用していても対象の分け方に難があったり、研究方法そのものに難があったりした。またこれらの論文で最も大きな弱点は救急隊による患者の追跡調査である。患者の特性であったり救急隊が以前経験したことが体系化されていない、対照データが設定されていないないなど、論文の信頼性を低下させるものである。
1本でも多くの論文を出すこと
本稿で引用した2つの論文では無作為コントロール研究のみを優遇しているようだが、症例報告だって立派な論文である。救急隊員シンポジウムに参加すると、全国には志の高い人たちがいろいろ先進的なことをやっているを目の当たりにする。そこで発表された演題が1つでも多く世の中に論文として発表されれば論文1つ分現場学が育って行く。プレホスピタルケア編集委員として、現場学を確立したいと思う救急隊員からの多くの投稿を期待している。
文献
1)Emerg Med J 2014;31:1016-24
2)Emerg Med J 2014;31:594-603
3)Acad Emerg Med 2004;11:790-3
4)Acad Emerg Med 2001;8:288-91


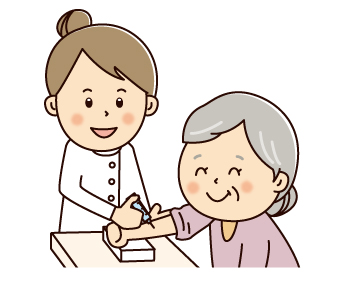

コメント